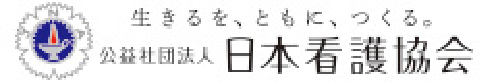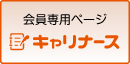本会では、いつでも視聴が可能なオンデマンド研修と、講師や受講生同士のリアルタイムでの双方向な関係構築が可能なリアルタイム研修、両者を組み合わせた研修を提供しています。
このページでは、それぞれの研修の特徴をふまえた上で、看護実践や施設内教育での活用方法についてご紹介します。
研修で学び、
実践に役立てるには
研修を活用した学び方や、実践への活かし方について紹介しています。生涯学習のひとつの方法として、研修を積極的に活用し、ぜひ日々の看護実践にお役立てください。
1.学ぶ目的を明確に!
実践の中の気付きを学びのきっかけにする
みなさんが研修に参加するきっかけは様々だと思いますが、日々の実践の中にこそ“気づき”があり、それが学びのきっかけとなります。その気づきを見逃さず、“気になったこと”や“疑問”の解決の糸口を見つけたい、または課題を明らかにしたい、他の人の意見を聞いてみたいなど、自分がどうしたいかをはっきりさせ、必要な研修を検索して参加することをおススメします。
ここで研修に参加した受講生の声を紹介します。
受講した研修「標準的な看護計画に基づくフィジカルアセスメント」
患者さんの苦痛に対し、適切なケアができずに悩むことがあった。病棟で勉強会にも参加したが、自分でも勉強してみようと考え研修を受講した。患者さんの身体に何が起こっているのか、観察ポイントに基づいてひとつずつ観察することが、苦痛の原因をアセスメントする第1歩だと分かった。
目の前の患者さんのケアについて抱える悩みが、研修受講のきっかけになっています。受講の際には、苦痛の原因を学ぶ、苦痛のある患者さんへの対応を学ぶなど、明確に目的を持つと学習効果も高まります。
受講した研修:管理者向けのリアルタイム研修
新たな役職に就いたことをきっかけに、新たな環境において自身の看護管理実践能力の向上をしたいとオンラインの研修に参加した。新しい環境で生じる課題解決に向け、新たな知識の獲得、他施設との情報交換等から解決の糸口を獲得することができた。
目的を明確にして研修に参加すると、課題解決の糸口を主体的に見つけようとするため、学習効果も高まり、研修受講後の実践にも活かせるようになります。
看護職として基盤となる能力、看護実践能力の向上を目指す
日常の実践の中から課題を見出し、研修を受講するだけでなく、安全な医療・ケアの提供に向けた看護職の活動の基盤となる能力の向上や、定期的にアップデートが必要な内容について、計画的に研修を受講することが大切です。
ここで研修に参加した受講生の声を紹介します。
受講した研修:「日常生活場面で理解する看護職の倫理綱領と看護業務基準2021改訂版」
担当する患者さんのケアについて他職種と意見が異なり、自分の考えや主張に迷いが生じ、この研修を受講した。倫理綱領の9番目にある「患者さんに対して最善を尽くすことを共通の価値とする」という言葉が腑に落ち、患者さんの意思を尊重しながら、他職種とより良い議論ができることが大切なのだと気づいた。今後も自分の看護について迷った時は、行動指針である倫理綱領に立ち戻り、実践と繋げて学ぶようにしたい。
看護職の活動の基盤となる、知識のアップデートに役立つ研修は以下を参考にしてください。
あらゆる場で実践を行う看護職を対象とした行動指針である「看護職の倫理綱領」を学ぶ
No.101「日常生活場面で理解する看護職の倫理綱領と看護業務基準 2021改訂版」
専門職として、専門性の強化や社会貢献のため、その社会的責務等を学ぶ
No.120「専門職の社会的責務と制度・政策の決定過程の理解と参画」
安全な医療およびケアを提供するために必要な基礎知識を学ぶ
No.118「医療安全の制度・施策の動向と法的基礎知識」
No.119「感染予防・対策の基本」
2.受講中の学び方が
今後の実践のカギを握る!
みなさんはどのように研修に臨んでいますか?講義を聴くだけでなく、積極的に質問をしたり、講義での学びからこれまでの経験に意味付けを行うなど、能動的な学びによって今後の実践に活かしやすくなります。
ここで研修に参加した受講生の声を紹介します。
受講した研修:「医療安全管理者養成研修」
法律や制度、指針に関しては、用語も聞き慣れず難しかったが、オンデマンドを繰り返し視聴し、確認したため、少しずつ言葉の理解ができるようになった。そして自組織の医療安全に関する指針や基準がどのような法律などに基づいて作成されたかを改めて知ることができ、指針や基準に基づいて行動する大切さを実感した。
受講した研修:「標準的な看護計画に基づくフィジカルアセスメント」
この研修は、事例をもとに演習シートを使ってアセスメントができるため、疾患や症状に応じた観察ポイントを書き出しながら演習シートに整理できた。実際の患者さんに対しても、演習シートに整理した観察の視点を想起して身体の状態をアセスメントすることができ、実践に活かすことができている。
能動的な姿勢で学ぶことは、単に受講したということにとどまらず、繰り返し視聴する、時間を空けて講義を再確認する、演習シートで学びを整理して確認するなど、自分に合った学習スタイルを発見できるようになるでしょう。自分に合った学習方法は、知識の定着を促進するだけでなく、定着した知識を今後の実践に活用することにもつながります。
3.学びを実践に役立てる方法を知り、
「学ぶ」と「実践」を循環させる!
学びは実践に活かしてこそ意味があります。同僚や上司に自分の学びを語り、意見交換をすることで内省が進み、新たな知識を定着させます。知識は定着すると、異なる場面でも活用できるようになります。
振り返りは、学びを意識化し“言葉にすること”が大切です。言葉にすることで、自分のできていること、できていないことを確認でき、次の課題が見えてきます。その課題を解決するために更に学び、チャレンジするという循環により、学びが蓄積し、実践に活かされ、ケアの対象者へ還元されることにつながります。
ここで研修に参加した受講生の声を紹介します。
リアルタイム研修受講生
Zoomミーティングを用いたリアルタイム研修では、双方向のやり取りが可能なため、グループワークで同じ悩みや課題について他の受講生と意見交換ができた。意見交換の内容を、自部署の同僚や上司と共有することで、日々の看護実践を振り返り、新たな取り組みを考える機会となった。
受講した研修:「ケアの受け手の状況に応じたフィジカルアセスメント」
この研修は、受講後に今後の取り組みたいことを記載する「看護実践能力強化を目指した実践シート」がある。その中の“明日から取り組めそうなこと”を思い切って先輩に伝えると、患者さんのケアを一緒に経験させてもらうことができ、できたこと、足りない点がはっきりみえて、次に学ぶべきことが分かってきたので、次の課題にチャレンジしているところである。
研修で得た学びを省察し、自分の中で意味づけを行い、次の実践でチャレンジしてみる。その循環により、螺旋的に能力を向上させていく力を自分なりに身につけていくことが重要です。
施設内教育への
研修活用方法の提案
施設内教育の取り組み例について紹介しています。研修の効果的・効率的な活用の実際を参考にし、ぜひ自施設の教育・研修企画にお役立てください。
1)リアルタイム研修の活用
(1)受講内容を参考に、施設内・部署内の勉強会を企画!
研修で行なった事例検討における思考過程を参考に、施設・部署内での勉強会・学習会の企画に活用できます。所属施設・部署の勉強会・学習会参加者と対象患者となる疾患等を想定しながら、所属施設で求められるアセスメント力を強化するための勉強会や学習会の企画に役立ててください。
≪2025年度研修例≫
「高齢者の“いつもと違う”を看護に活かす」
シリーズ①夜、眠れない高齢者
シリーズ②胸が痛いと訴える高齢者
シリーズ③腹痛を訴える高齢者
≪勉強会・学習会の企画のポイント≫
・自施設や自部署で対象となる患者を想定し、自分たちが遭遇する高齢者のよくある事例を設定します。
・患者の状況をふまえ、情報収集やケアにつながるアセスメントができるよう、事例の経過をいくつかの場面に区切り、その都度、アセスメントするためのポイントを明確にします。
・事例の場面設定ごとに、参加者がより深くアセスメントできるようなファシリテーション方法を工夫します。
・勉強会や学習会の時間設定に応じて、事例の経過をいくつかの場面に区切り、考える時間を設定します。
・受講内容を所属部署での勉強会・学習会の企画にぜひ活用してみてください。
(2)研修での学びを、日々の実践に活用!
①看護実践への活用
研修受講生への終了後のアンケート結果によれば、研修内容を後輩への指導や日々のカンファレンスに活用した方が約6割となっています。自身の学びだけでなく所属部署の教育や看護実践に活かされています。
≪2025年度研修例≫
倫理カンファレンスのあり方・進め方
・症例を取り上げて事例検討を行う研修を受講した場合には、研修で活用したガイドライン等を参考に受け持ち患者のアセスメントや支援の方法を話し合ってみましょう。
・研修で得た新たな情報や他施設での取り組みを、カンファレンスの時間に共有してみてはいかがでしょうか。
②看護管理実践への活用
研修では自施設や自部署の問題を整理し、問題解決に向けた方策の検討を行います。研修受講生や講師とのディスカッションを通して得た意見や問題解決のための新たな発見を、自身の看護管理に活かすことができます。
2)オンデマンド研修の活用
(1)オンデマンド研修での均質的な学習にグループワークを追加し、実践に活かす学びを実現!
経験年数の短い看護職が多いA病院では、患者さんの状態変化に気づく力を向上させたいと考えていました。そこでオンデマンド研修と、実践的な事例を用いたグループワークを組み合わせた研修により、学びを実践につなげる取り組みを進めています。
自施設の教育計画には、看護実践能力の向上を目指したオンデマンド研修を組み込みました。導入前は、研修の企画から講師まで看護師長などが担っていましたが、講師ごとに内容も変わることもありました。そのためオンデマンド研修で、同じ内容の学習をすすめています。
看護実践能力のうち、臨床実践能力の「意思決定を支える力」と「ニーズをとらえる力」に関連が深い研修に関しては、自施設で一部事例検討やレポート提出を組み込むこととしました。受け身で受講するだけでなく、レポート等を用いて言語化することで学びが深まります。
講義を聴いた後、普段の実践を振り返るなど意見交換する時間が重要です。講義とグループワークを組み合わせ、オンデマンド研修の学びと実践をつないでいます。
(2)スタッフの興味関心に合わせたオンデマンド研修の活用から目指す「学習する風土づくり」
子育て中の看護職が多く、教育背景も多様な看護職で構成されるB病院では、多様な働き方を支援しながら、教育を継続できる仕組みを構築したいと考えていました。そこで、まずは学習する風土づくりを目指し、オンデマンド研修を学習の道具として活用することから始めています。
オンデマンド研修を、それぞれの働き方に合わせて、勤務の合間を活用し分割受講したり、繰り返し受講するなどしています。学習意欲があっても外部の研修に参加する時間が確保できない看護職も、自分に合ったスタイルで学ぶことができます。
オンデマンド研修を導入するだけでは、各自が自発的に学び続けることは困難です。活用を進めるために、休暇をとらずに受講でき、勤務内に少しずつ学べるといったメリットを周知することや、各病棟にパソコンやタブレットを配布するなどの受講環境を整えました。
スタッフの興味関心にあわせた学習をきっかけに、内発的動機付けが促進し、自発的な研修受講に繋がり人材育成に役立っています。
(3)オンデマンド研修で最新動向や制度の趣旨をとらえて、施設での検討・取り組み等に反映
高度急性期医療を提供するC病院は、様々な制度について自施設への適応を検討する際には、基礎的な知識をオンデマンド研修で理解し、最新の国の動向やその背景などを確認しています。また、最新の知識にアップデートする方法としても、オンデマンド研修を活用しています。
院内の基準や新しいチームの立ち上げなどを検討する際、病院・看護部の理念や方針に基づき考えることに加え、推進する管理者や各委員会が、オンデマンド研修を活用し、背景や基本的事項を踏まえたうえで協議します。
C病院では、個人の主体的な学びを大切にしています。しかし同時に、専門職として情報をアップデートしていく責務があると考え、オンデマンド研修から必要な研修を選定し受講促進をしています。
また自施設内での研修企画時にも、研修担当者が視聴し、最新の情報や背景などを把握して、プログラムの設計に役立てています。
(4)オンデマンド研修の活用で、看護職の段階的な能力を支援!
地域の中核病院のD病院では、特定の領域に関わらず幅広い知識と技術を身に付けた看護師を育成したいと考えています。そこで看護実践能力をバランスよく育成するために、自施設の人材育成に「看護師のクリニカルラダー(日本看護協会版)」(JNAラダー)※を参照し、看護実践能力の向上を支援しています。
※現在は、看護実践能力習熟段階(看護師のまなびサポートブック参照)
目指す看護師像を明確にしたうえで、自施設の看護師に必要な看護実践能力とその他の能力を整理して自施設のクリニカルラダーを作成しました。それに基づく教育計画は、オンデマンド研修も活用して立案・実施しています。
本会の研修は、看護実践能力のどの能力に紐付くかが分かるようになっているため、段階的な学びに活用できます。また、オンデマンド研修の受講の後には、自施設の特性に合わせた実践に活かせるよう、各レベルに応じてグループワークやカンファレンス等を組み合わせています。
対象に合わせたおススメの研修
すべての看護職が安全に看護を提供するために必要な研修
専門職としての活動の基盤となる、看護職としての職業倫理や医療安全、感染管理は、活動する領域や職種を問わず、また習熟段階に関わらず定期的な知識や技術の更新が重要です。
離職・休職中の看護職にも受講をお勧めします。
2025年度配信する研修
| No. | 研修名 |
|---|---|
| 101 | 日常生活場面で理解する看護職の倫理綱領と看護業務基準 2021改訂版 |
| 118 | 医療安全の制度・施策の動向と法的基礎知識 |
| 119 | 感染予防・対策の基本 |
| 120 | 専門職の社会的責務と制度・政策の決定過程の理解と参画 |
介護施設、訪問看護ステーション等で働く看護職の方々の実践に役立つ研修
本会で提供している研修の多くは、受講対象の活動領域を限定していません。以下のように、施設や訪問看護ステーション等での活動に密着した内容の研修も多数あります。
また、オンデマンド研修、リアルタイム研修のどちらも研修場所への移動がないため、現場を離れにくい介護施設や訪問看護ステーション等で勤務する方々から好評を得ています。ぜひご活用ください。
2025年度配信および開催する研修
| 看護チームで共に学ぶと共通理解が深まり、 ケアに活かせる研修(准看護師の方にもおススメ) |
|
|---|---|
| No.110 | 介護保険施設で生活する高齢者の支援に必要な知識とケア |
| No.115 | 看護チームにおける業務のあり方(基礎編:看護師の責務) |
| No.122 | ①看護に生かす褥瘡予防の基本/ ②誤嚥性肺炎を予防する口腔ケアの基本 |
| No.123 | ①感染予防の基本2023/ ②誤嚥を予防する食事介助の基本 |
| 異常のサインが表れにくい高齢者の状態を アセスメントし、ケアを導き出すプロセスを学ぶ |
|
| No.107 | 高齢者の“いつもと違う”を看護に活かす ~夜、眠れない高齢者~ |
| No.108 | 高齢者の“いつもと違う”を看護に活かす ~胸が痛いと訴える高齢者~ |
| No.109 | 高齢者の“いつもと違う”を看護に活かす ~腹痛を訴える高齢者~ |
| 地域で暮らす高齢者を支えるための看護職、 多職種との連携を学ぶ |
|
| No.113 | 地域で暮らす高齢者を支える看護職連携の実際 |
| No.114 | 複合的な問題を抱えながら地域で暮らす高齢者を支える看護職・多職種連携 |
外来や診療所で働く看護職の方々の実践に役立つ研修
在院日数の短縮化や医療技術の進歩もあり、入院医療と在宅医療の間に位置する外来医療が担う役割や機能は、多様化・高度化しています。また、地域包括ケアの推進において、地域で生活する医療を必要とする人々の重症化予防には看護師の支援が欠かせません。在宅療養支援の力をつけるため、ぜひ、本研修をご活用ください。
2025年度配信する研修
| No. | 研修名 |
|---|---|
| - | 外来における在宅療養支援能力向上のための研修 |
看護管理を実践する方々に
役立つ研修
看護管理者として、新たな役割を担う方、現在マネジメントを実践している中で、課題を抱えている方などにおすすめです。