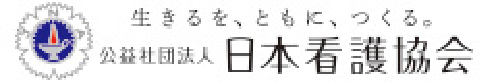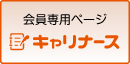日本看護協会が提供する研修
日本看護協会では、「看護職の生涯学習ガイドライン」(2023年6月発出)を羅針盤とし、以下の新たな基本方針や研修分類に基づき、生涯学習の支援として、看護職個々への研修を提供するとともに、看護職を雇用する施設への研修提供や都道府県看護協会と連携した研修提供を行います。
生涯学習、生涯学習支援については、以下をご覧ください。
生涯学習支援
基本方針
公益社団法人日本看護協会(以下、本会という)は、看護の質の向上、安心して働き続けられる環境づくりの推進、人々のニーズに応える看護領域の開発・発展を図ることにより、人々の健康で幸福な生活の実現に貢献することを使命としている。この目的に向け、定款第4
条の7 事業の一番目に「教育等看護の質の向上に関する事業」を挙げている。
看護職が活躍する領域や場は多様化し、看護職の役割発揮に対する社会からの期待は高まっている。看護職が人々の期待に応え役割を発揮するためには、主体的に継続的な学習に取り組み、能力の開発・維持・向上を図り続ける生涯学習が重要になる。
そこで本会では、生涯学習の羅針盤となる「看護職の生涯学習ガイドライン」を策定するとともに、生涯学習の支援として看護職個人への学習機会の提供と各施設向けの研修提供を行う。また、研修の企画実施にあたっては、都道府県看護協会と常に連携・協働して実施する。
具体的には、看護職個人への学習機会の提供として、①専門職としての活動の基盤となる研修、②看護・医療政策に関する研修、③人材育成や教育支援を行う者を対象とした研修、④看護管理者を対象とした研修、⑤資格認定教育を行う。また、各施設向けの研修提供として、施設内教育の際に活用できる研修教材の制作・提供を行い、看護職の生涯学習を支援する。
研修分類
本会では、新たな基本方針に基づき、看護職に必要な内容を網羅的に提供するのではなく、以下の5つの分類に沿い焦点化して提供します。
| 分 類 | 内 容 |
|---|---|
| 分類1. 専門職としての活動の基盤となる研修 |
習熟段階や活動の場、役割等を問わず、すべての看護職の活動の基盤となる研修を提供 |
| 分類2. 看護・医療政策に関する研修 |
最新の情報も踏まえた看護・医療政策に関する研修を提供 |
| 分類3. 人材育成や教育支援を行う者を対象とした研修 |
看護職の主体的な学びを支援する方の育成・支援を目的とした研修を提供 |
| 分類4. 看護管理者を対象とした研修 |
看護管理者としてより良く働くための環境整備に必要な労務管理に関する知識をはじめ、組織管理等に関する研修を提供 |
| 分類5. 資格認定教育 |
日本看護協会では、認定看護師教育課程(6分野)、認定看護管理者教育課程(サードレベル)の教育を実施 |
日本看護協会では、提供する研修について、看護職に求められる能力のうち、看護師および助産師については、それぞれの職種に求められる「看護実践能力」「助産実践能力」レベルを提示しています。また、活動する領域や職種を問わず、安全に看護を提供するために定期的な知識のアップデートが必要な研修も示しています。
看護管理者とその候補者には、「病院看護管理者のマネジメントラダー日本看護協会版」で示される6つの能力の定義を基に研修を提示しています。
また、実践能力習熟段階(看護師・助産師)や病院看護管理者のマネジメントラダー、専門看護師・認定看護師・認定看護管理者のそれぞれの関係性を図示しました。(保健師については追って掲載予定)
図では1人の看護師が国家資格を取得し、就業後に実践能力を習熟させていく段階を示すとともに、看護管理者、専門看護師・認定看護師等のキャリアの選択も含めたイメージを記載しています。
なお、下の図は、病院看護管理者のマネジメントラダーのⅢやⅣの人が看護実践能力習熟段階および助産実践能力習熟段階のⅣである、ということを示すものではありません。
◆「看護実践能力習熟段階」「病院看護管理者のマネジメントラダー」「日本看護協会認定資格」のイメージ図

◆「助産実践能力習熟段階」「病院看護管理者のマネジメントラダー」「日本看護協会認定資格」のイメージ図

詳しくは以下をご覧ください。
看護実践能力
助産実践能力
病院看護管理者の能力