- ホーム
- 看護職の皆さまへ
- 資格認定制度
- 資格認定を目指す方へ(資格について)
- 専門看護師
- 専門看護師の活動事例紹介
- 坂木 晴世さん
坂木 晴世さん
坂木 晴世さん 感染症看護専門看護師
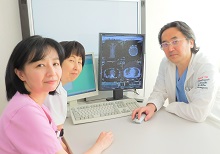
所属施設
国立病院機構西埼玉中央病院 看護部
埼玉県所沢市若狭2-1671
病院病棟数:6病棟 許可病床数:325床
看護師数:214名(専門看護師1分野2名・認定看護師6分野7名)
※2019年3月現在
資格取得までの道
現在の所属施設に就職後、2002年に感染管理認定看護師資格取得
非常勤で専従の感染管理認定看護師として週に2日勤務しながら、
大学院修士課程へ進学。その後、大学院博士後期
課程へ進学・修了後、復職。
2009年資格取得
活動紹介
日々の実践の中で心掛けていることは、個と集団を同時に俯瞰したリスクヘッジです。感染症看護は守備範囲の広い領域です。たとえば、発疹を主訴に来院した患者に麻疹が疑われると、医師や看護師から相談を受け、アセスメントと感染対策を並行して行います。麻疹と診断されると、保健所へ報告しますが、それで終わりではありません。保健所と連携し、地域での拡大防止のための情報共有や、感染リスクのある人々の対応に関する相談を受け、対策を行うとともに、患者個人に対するケアマネジメントや倫理的問題からの擁護を行います。感染症には、二次感染のリスクやアウトブレイクといった他の疾患にはない特有の問題があります。感染拡大のためには迅速に対応する必要がありますが、確定診断前の動きには制約があり、配慮が必要です。保健所や地域の医療機関との情報共有によるシームレスな医療提供システム、患者への直接ケア、家族や職員の二次感染予防が遅滞なく実施されるように調整が必要です。
私が日々の実践で関わる人々は、患者はもちろんのこと、医療従事者や患者の家族および面会者などの病院に出入りする人々、近隣の医療機関やケア施設、保育園や学校を含む一般市民、そして公衆衛生に関連する機関の人々と多種多様です。また、国際化による輸入感染症の台頭、高度医療の発展や超高齢化による易感染患者の増加、地域包括ケアの推進による医療関連感染リスクの変化など、感染症を取り巻く環境は十数年で大きく変わりました。今や、単一の医療機関だけで感染対策を行うことは困難で、多施設・多職種の関係者と幅広く連携することが不可欠です。これまでの経験の中で、私が感染症看護専門看護師として得た知見は、私たちが果たせる役割が決して小さくないということでした。
専門看護師の役割の一つに研究があります。感染管理活動の拠り所となる学術論文には、エビデンスレベルの高い研究が多いとはいえません。NICUの副看護師長であった頃、NICUには感染管理の改善につながる看護系の論文が少ないと感じていました。私が大学院に進学したのは、看護のアウトカムを検証し、効果的なケア方法を見出すための研究をしたいと考えたからです。修士課程では、自施設のデータを解析した結果、新生児の結膜炎と眼脂の関連を見出しました。この結果に基づいたアイケアの実践は、結膜炎の減少に繋がったと考えます。しかし、単施設の研究は一般化可能性が低いため、このケアの検証を他施設でも行うことが必要です。
また、中心静脈ライン関連血流感染予防のためのライン挿入時のマキシマルバリアプリコーションは、成人を対象としたランダム化比較試験の結果に基づき実施が強く推奨されています。しかし、現状では新生児を対象としたエビデンスがないため、日本の臨床においては議論のある対策として標準化されているとはいえません。この問題を解決するために、医師を含む研究チームで多施設協働研究を行い、低出生体重児におけるマキシマルバリアプリコーションの有効性を示唆する結果を得ることができました。今後は、実践レベルの課題を克服しつつ、実施の標準化に努めていきたいと考えています。
より良い方策を打ち出すためには、臨床的意義のある、質の高い研究が必要です。論文を紐解き、実践に活用しながら、臨床の疑問をリサーチクエスチョンに変換し、自らが研究活動をすることが、専門看護師の実践として意義があると考えます。臨床には多くの疑問と、検証すべきデータがあります。これからも、EBPの実践と日本から研究成果を発信する取り組みを続けていきたいと考えています。
所属施設の上司から受けた支援

私はNICUの副看護師長として勤務していましたが、進学を理由に退職し、非常勤で専従の感染管理認定看護師という前例のない職位を申し出ました。今考えれば、かなり無茶な申し出だったとは思いますが、それを受け入れてくれたのは看護部長でした。
当院の歴代の看護部長には、常に専門看護師として自律した活動ができるように支援していただきました。感染症看護専門看護師は、院内で横断的に、そして院外の様々なフィールドで専門家としての役割を求められます。異なる職種の中で人的資源として活用してもらえるように、看護部長を筆頭に、院長はじめ病院幹部職員が私の専門性を認め、施設内外における横断的な活動を受け入れてくれていることが、何よりも大きな支えであると感じています。
上司からのメッセージ
土渕 真紀子さん(西埼玉中央病院 看護部長)
坂木さんは当院で2002年の早い時期より専任の認定看護師、2012年からは専従の専門看護師として勤務しています。現在、専門看護師は坂木さんを含め2名おり、1名は病棟配置の専任として勤務しています。一般急性期病院325床の当院で2名の専門看護師の人材に恵まれて、コンサルテーションのほとんどは医師であり、信頼度は絶大です。タイムリーに最新情報の把握や職員教育や自己研鑽に意欲的な活動をしており、他の認定看護師・専門看護師のロールモデルになっています。また、地域保健医療の推進でも、豊富な感染管理の経験とプレゼンテーション力の高さから多方面からの依頼が多く重要な役割を果たしています。本人と活動の範囲を吟味し、業務分担や感染対策チームとの連携もタイムリーに調整しながら、今後も常に活動しやすい環境を整備し支援し続けたいと考えております。
(2019年7月30日掲載)
前へ戻る
