常任理事のマンスリー通信
機関誌「看護」2026年2月号より
常任理事 井本 寛子
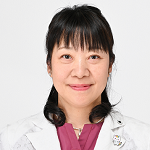
女性とその家族への健康支援に関する情報サイトをご活用ください
わが国では女性の社会進出が進み、就業率が増加しています。一方で、女性の平均寿命と健康寿命の間には約12年の乖離があり、半数以上の女性が月経関連の不快症状等、女性特有の健康課題を抱えています。これに伴う社会全体の経済損失は約3.4兆円と推計されています。看護職には就業場所にかかわらず、これらの健康課題を抱えた女性への健康支援が求められています。特に助産師は、女性の生涯における性と生殖にかかわる健康相談や教育活動を通して家族や地域社会に広く貢献する専門家であり、保健師など地域の多職種との連携の下、全世代を対象に必要な支援を提供することが期待されています。しかし、助産師の多くが医療機関に所属しているため地域での活動が難しく、支援を届けにくい状況です。女性の健康支援の必要性について新たな動画を作成しましたので、組織の体制構築に情報サイト(※)をご活用ください。
常任理事 木澤 晃代

A課程認定看護師教育を2028年度末まで延長します
日本看護協会は、2020年度に特定行為研修を含んだB課程教育を開始しました。2024年度に認定看護師教育機関や関連学会等に調査した中間評価では、時間数の増加、実習施設の確保困難や教員の負担増等により、教育機関の維持継続が困難であること、専門分野の教育が希薄化したことなどが課題として挙げられました。A課程からB課程への移行が困難であるため、閉講する教育機関があることも大きな懸念事項です。また、特定行為研修制度のあり方が変化している状況において、さらに専門性の高いレベルで活躍する認定看護師を養成するためには、新たな視点を取り入れて、課題解決に向けB課程教育を発展的に見直す必要があると判断しました。2028年度開始に向けてB課程教育を見直すに当たって、関係各所への影響の大きさを鑑み、2026年度末終了予定のA課程教育を2028年度末まで延長し、B課程教育について十分な検討を行うこととしました。詳細は、随時情報提供していきます。
常任理事 田母神 裕美

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の推進
オンラインセミナーの開催
2025年10月に「看多機開設運営支援オンラインセミナー」を開催しました。セミナーには約400人の皆さまの参加をいただきました。2025年に1,100事業所を超えた看多機ですが、今後さらに設置推進が求められるサービスです。セミナーでは3人の看護管理者の皆さまに、看多機開設と経営の実際について講演いただき、開設から運営が軌道に乗るまでの過程で課題に直面しながらも、管理者と職員が一丸となって目標を設定し、計画を実行して解決につなげるプロセスをお示しいただきました。また、行政の立場から看多機の設置促進に向けた取り組みとして、市全域を対象に看多機の公募推進を行ったこと等をご報告いただき、看多機のケアが高く評価されていることを感じました。訪問看護、訪問介護、通い、泊まりの機能を持つ看多機が、中重度の要介護の方が「住み慣れた居宅を中心に」した療養を継続できるよう支えていることを多くの皆さまにご理解いただき、必要とする方の利用につなげていかなければなりません。
常任理事 松本 珠実

生活保護受給者の健康管理支援について
2025年10月から4回にわたり、「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」が厚生労働省主催で行われ、このたび、中間的な整理が取りまとめられました。生活保護制度は、受給者の最低生活の保障と自立の助長を目的としており、受給者は、国民健康保険の被保険者から除外されているため、ほとんどの医療費は医療扶助で負担されています。2023年の生活保護費負担金は50%以上が医療扶助となっていますが、その要因として、受給者の高齢化があり、市町村国保と比べて生活習慣病の外来受療率が高く、外来受診日数や医薬品の種類数が多いことなどがあります。整理では、効果的な対策について、自治体における計画的な事業企画、評価指標の標準化、広く住民に行われている健康づくりの活用、福祉事務所の事務手続きの簡素化やICT化、自治体保健師との連携推進などが掲げられています。看護職としてエンパワメントに資する支援を行い、ケースワーカーと連携することが大切です。
常任理事 橋本 美穂

働き方やキャリア形成に役立つ情報を発信するウェブサイトをリニューアル
看護職のキャリアをサポートするポータルサイト「NuPS(ナップス)」は、2026年秋以降に稼働を予定しています。NuPS稼働後は、看護職としての経験や学びをサイト上でまとめて管理でき、働く場所が変わったり、働くことをお休みしたりすることがあっても、生涯にわたり自分の看護職キャリアの証明として、持ち歩くことができます。これに先立ち、働き方のヒントやキャリアアップのポイントなどの情報を掲載したウェブサイトをリニューアルオープンしました。サイト上でメールアドレスを登録すると、「看護職として働く」ことに役立つ最新情報が届きます。また、これから看護職になる看護学生も登録できます。看護職としての充実したキャリアをめざし、よい最初の一歩が切れるよう、看護学生へのご紹介をお願いします。
常任理事 淺香 えみ子

「看護人材・夜勤人材の確保に向けた看護職の多様で柔軟な働き方導入支援セミナー」開催
看護職のウェルビーイングを意識した労働環境整備に向けて、多様で柔軟な働き方の導入に関する第1回セミナーを開催しました。働き方の側面からの提案として“多様性と柔軟性“を就業スタイルに取り入れる方法を共有。現場の働き方改革は、組織の規定や業務特性、働く看護職の条件などの多くの要素を考慮する必要性から、着手が困難との声があります。一方で、先駆的に改革を進め看護職の定着や確保に成功した施設があります。本セミナーでは、そうした施設の成功のポイントとなる考え方や方法を参加施設が抱える課題や工夫とともに共有し、自施設に活用できる手段を持ち帰っていただきました。事後アンケートでは「画一的な方法からの突破口を見いだす機会として他施設との情報交換が有用」との声が寄せられました。組織ごとの事情の中で取り組みを進めていくポイントをまとめた「多様で柔軟な働き方導入応援ブック」の作成を進めています。情報交換の場とともに広く活用いただけるよう準備しています。
よりよいウェブサイトにするために
みなさまのご意見をお聞かせください

