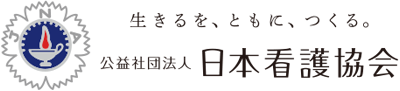助産師の活動
更新日:2021年2月18日
コロナ禍での家族形成を支える助産師の関わり
社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院
総看護部長 森本俊子さん / 看護部次長 中村典子さん
産科病棟課長 池田千夏さん / MFICU課長 齋藤貴子さん
72の診療科を持つ地域医療の拠点であり、総合周産期母子医療センターの指定も受けている社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院。同センターの助産師たちは、新型コロナウイルス感染症の発生から第1波において、妊産婦向けの集団指導をいち早く実施し、オンラインで公開する動画なども活用しながら妊産婦や家族のサポートを続けている。
職員と母子をサポートする体制づくり
静岡県内で新型コロナウイルスの検査陽性者が確認された2020年2月、同院では、感染管理室と病院幹部を中心に対策の検討を始めていた。病棟の整備やマニュアルの作成などを進め、病院玄関での体温チェックや面会制限などの対応を行った。職員に対しても、休憩室の分離やメンタルサポートチームによる相談対応をしたほか、家族への感染を恐れて自宅に帰れない人には宿舎を手配した。森本俊子総看護部長は「スタッフに少しでも心地良く働いてもらえるよう、宿舎の備品に配慮したり衣服の替えなどを用意したりしました。院内の休憩室をはじめ、スタッフの快適性やアメニティを考え直す機会になりました」と話す。
周産期については、院内だけでなく近隣の3つの地域周産期母子医療センターと同院を含む4病院で連携し、対策を話し合った。それを基に、発熱がある妊産婦のトリアージや感染管理に向けたNICU・MFICUのゾーニング、対応する人員体制の整備などを行った。応援の体制や対応マニュアルもひんぱんに見直し、最新の内容を共有。さらに、感染管理認定看護師を中心に、産科病棟やMFICU、GCU、手術室のスタッフで、陽性者が対象になった場合の帝王切開術やNICUへの搬送経路の確認などの実践的なシミュレーションも実施した。
中村典子看護部次長は「さまざまな対応を同時進行で行う必要がありましたが、現場の対応は早かった」とスタッフに感謝する。産科病棟の池田千夏課長も「最初に感染症対策の担当者を決める時、負担も大きく不安もある中で、ほとんどのスタッフがスムーズに引き受けてくれました」と語る。
オンラインも活用し家族に寄り添う

感染管理認定看護師の指導を受けて
対応のシミュレーションを実施
感染が拡大する中、家族の分娩立ち合いや面会が制限され、母親学級も3月には休止となった。そこで、母親学級については、助産師らが指導内容をまとめた動画を作成し、同院のHP内で公開した。妊娠中から産後、退院後までの時期ごとや、初産婦・経産婦などのケースごとに必要な情報をリストアップし、議論しながら取り組むことで、助産師の知識もブラッシュアップできたという。また、産後の2週間健診ができなくなった時期は電話相談に切り替え、状況に応じて行政の保健師にも小まめにつないだ。
同院では、陣痛開始時から分娩までをLDR(陣痛分娩室)の1室で過ごすが、家族の立ち合いがない中、常に誰かが寄り添えるよう、助産師の数も徐々に確保していった。齋藤貴子MFICU課長は「MFICUに入院している母親は、大きな不安やさみしさを抱えています」と話し、助産師が積極的に赤ちゃんのいるNICUに同行するなど、より丁寧な対応を心掛けた。
6月には産科で感染疑いの妊産婦を受け入れたが、すでに病床のゾーニングやシミュレーションなどを終えており、落ち着いて対応することができたという。今後も地域の感染者数などの状況に応じ、面会の制限や緩和を検討するほか、産後うつの増加がないかなども注視していく。
これまでも同院では、助産師らが一丸となって多様なケースの妊産婦を受け入れてきた。厳しい状況が続く中、森本総看護部長らは「新しい家族形成の場面で、助産師の関わりはとても大切です。総合周産期母子医療センターとしての気概を持って支援を続けていきたい」と、決意を新たにしている。
(2021年2月15日確認)
地域のネットワークを生かし最前線で母子に寄り添う
みやした助産院 院長 宮下美代子さん
神奈川県横浜市の住宅街にたたずむ、みやした助産院。経験豊富な宮下美代子院長を中心に、8人の助産師が産後母子ショートステイ(入院)やデイケア、母乳外来、各種教室なども含めたさまざまなサービスを提供している。
毎年、多くの助産(看護)学生や病院に勤務する助産師の研修も受け入れており、宮下院長は講演会や指導などで全国を飛び回ってきた。新型コロナウイルス感染拡大は、そうした活動にも影響を与えたが、宮下院長は「たくさんある教室の振り返りや事業の見直しなどを行っており、今後、妊産婦の皆さんに向けた新たな活動が展開できれば」と考えている。
母子と職員を守る体制づくり
同助産院では、県の助産師会をはじめ各団体からの情報を基に感染対策を進めてきた。衛生用品はインターネットを通じて一定数を注文・確保したが、最も不足感があった2020年3月ごろには、県や市からマスクやゴーグル、ガウンなどを手に入れることができた。宮下院長は「これまでつちかってきた団体や地域とのネットワークが生きました」と語る。
感染対策は、職員とのカンファレンスで優先順位を決め、体制整備から始めていった。同助産院の助産師8人のうち、妊婦だった3人には早めに産前産後休暇に入ってもらい、その他の職員は時差出勤に変更した。事務職はリモートでの勤務も導入。通勤も、電車でなく助産院が持つ家庭訪問用の車を使うなど、できる限り感染のリスクを減らすようにした。
妊婦健診や母乳外来では、母親同士の予約が重ならないように予約枠を整理し、家族の同行を避けてもらうよう依頼した。産前・産後の面会については、母子の健康や精神状態などの様子を見て完全には制限せず、可能な範囲で続けた。
出産時に家族の立ち合いがなかった母親には、できる限り助産師が付き添うことで「ずっとそばにいてくれて、安心感があった」との声をもらった。
サービスの縮小や休止で経営が厳しくなった時期もあったが、宮下院長は母子の安全に最大限の注意を払うとともに、職員にも「一時、勤務時間が減るかもしれないが、皆さんの安全や立場を保証する」と伝えて協力を仰いだ。1日に勤務する職員数は減ったが、互いに業務をカバーしあう意識が高まり、これまで講演会や講義などで外出が多かった宮下院長が院内にいることでスムーズな調整やサポートを行うことができた。
それぞれの不安を丁寧に受け止め対応

感染対策を行いながら母子のケアを続ける宮下院長
同助産院では以前から、不安が強かったり外出が困難な母親向けにオンラインでの相談サービスを行っていたが、感染拡大をきっかけに、発熱した妊産婦へのリモート指導も行うようになった。「利用者は数人でほとんどが乳腺炎でしたが、熱がある授乳中の母親がどこに電話しても対応を断られるという時期があり、この仕組みが活用できました」と振り返る。
このころには、総合病院で出産予定の妊婦から、家族の立ち合いが叶わなくなったため同助産院で出産したいという相談も数例あった。助産師らは、母親の不安や希望をしっかりと受け止め、それまで通っていた医療機関で話し合ってみるよう促した。各団体から、事前にこうした事例に対する情報提供があり、出産する場所が二転三転しないよう丁寧に向き合うことを心掛けたという。
同感染症の流行が続く現在、宮下院長が気になっているのは、子どもの虐待に関する問題だ。寄せられる相談の中には緊急に対応が必要なケースもあり「コロナ禍の陰で、大きな影響を受ける存在がいることを身に染みて感じています」と訴える。また、以前から、産後、自宅に戻った母親や、孤立しがちな母親への支援を続けていくことの難しさを感じており「こうした人々を、地域の中でどう守っていくかが今後の課題です」と語る。さまざまな課題が顕在化する中、地域の最前線で活動する助産師として、一人一人の悩みに寄り添い続けている。
(2021年2月1日確認)
よりよいウェブサイトにするために
みなさまのご意見をお聞かせください