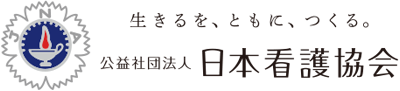- ホーム
- 看護職の皆さまへ
- 危機管理
- 新型コロナウイルス感染症関連情報
- 新型コロナウイルス感染症での看護職の活動
- 中小病院、一般病院での活動
中小病院、一般病院での活動
更新日:2020年8月7日
小児の特殊性を踏まえた新型コロナウイルス感染症対策の工夫
神奈川県立こども医療センター 感染管理認定看護師 秋葉和秀さん
神奈川県立こども医療センターは、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた県の医療体制において、高度医療機関に指定されている。小児三次救急医療を担い、高度専門医療を必要とする小児患者が多くいることから、ECMO(体外式膜型人工心肺)を要する場合など重症感染症の受け入れのみが想定されている。同院でなければできない手術や治療を止めないために、新型コロナウイルス感染症を院内に持ち込ませないこと・拡げないこと・職員がもらわないことを目標に対策をとっている。
子どもへの影響を避けながら対策を強化

看護師に廃棄物の分別と
配置を説明する秋葉さん(右)
同院では、感染管理認定看護師の秋葉和秀さんを中心に、臨時の院内感染対策会議を頻繁に行い、多職種で検討を重ねてきた。中でも最もこだわったのは、家族面会を完全禁止にはしないことだ。小児医療において、家族は病棟への単なる訪問者ではなく看護ケアのパートナーであり、入院する子どもに身体的・精神的な影響を与えるため、時間や人数などの制限は一部に留めた。具体的には、面会人数は2人まで、各面会者の面会時間は、医療従事者ではない面会者がマスクを鼻まで覆い正しく着用し続けられる時間を考慮し2時間までとして、面会を継続した。面会に関する基準は、定期的な会議の中で流行状況に応じて適宜変更している。
小児の新型コロナウイルス感染症発症の原因は家庭内の伝播が大半を占めることが分かりつつあったため、院内にウイルスを持ち込ませないよう対策の強化に向けて、正面玄関での全入館者に対する健康チェックも行った。全入館者の体温と接触歴、充血や味覚障害などの症状について問診票を基に職員が確認していった。もともと、入院患者と面会者の健康チェックは行っていたが、外来患者と家族、病院を出入りする業者など全入館者にチェックを拡大した。
対策強化の際、課題となったのは、多くの人的資源を必要とすることと、入館までに時間がかかることだった。健康チェックが軌道に乗るまでは、チェック方法や動線についてICT(感染制御チーム)だけではなく、病院長や副院長、事務、看護局と毎週評価・検討を行い改善していった。同院のサイトに問診票を載せて事前に記入できるようにしたり、記載スペースや問診票を確認する場所のレイアウトを変更したりすることで、今では当初の半分以下の人員で健康チェックを行うことができるようになった。
手指消毒剤とPPE(個人防護具)に関しては、同院でも物資不足に悩まされた。小児は成人と比べて抱っこや哺乳・食事介助など濃厚接触の機会が多く、手指消毒薬とPPEの使用頻度が非常に高い。平時の使用状況ではあっという間に底が尽きてしまうため、使用場面を再検討したり接触する際は一度にできることを行ったりと業務の調整を行った。また、支援物資のアルコールが届くようになってからは、そのまま使用するのではなくグリセリンや尿素を配合して使用する職員の手荒れにも配慮した。
今後に備え マニュアル作成や医療資源の確保へ

PPEの使用方法について
説明する秋葉さん(左)
こうした対応に追われる中、同院では小児の疑似症例の終末期の対応を経験した。今後、小児でも陽性者の看取りの対応を行う可能性も否定できないため、医師や急性・重症患者看護専門看護師、緩和ケア認定看護師など多職種で検討し、看取りや面会方法、退院時の経路に関するマニュアルを作成した。
小児は患者のみで受診することがないため、面会者などの持ち込み防止策を強化することが重要になる。また、PPEや手指消毒剤の供給不足は成人と比べてより深刻な問題だ。秋葉さんは、新型コロナウイルス以外のウイルスへの感染防止も考慮しつつ使用方法を定め、供給についてはさまざまな支援が受けられるよう発信していく必要があると考えている。
(2020年8月4日確認)
小児重症患者を受け入れるために 〜コロナ対応病棟再編と看護職のチーム力向上〜
千葉県こども病院 看護局長 浮ケ谷芳子さん
副看護局長 山岸聡子さん
県内の小児医療の重要な拠点である千葉県こども病院(224床)では、一般病院では治療が難しい特殊疾患や重症患児に対する診断・治療をはじめ生活支援、相談指導を行っている。同院をかかりつけとする患児たちには人工呼吸器等を着けて在宅で療養する子どもたちも多い。こうした子どもたちが新型コロナウイルスに感染したときのため、同院では2つの病棟を再編成した。1つは感染疑い患者や軽症者も含めて受け入れる「トリアージ病棟」の新設、もう1つはICUを2つに分け、通常のICUと重症化した感染者用のICUに再編成したことだ。
“感染は自分たちの責任のように感じる”
「トリアージ病棟」(10床)となったのは、全室個室のA病棟。主に緊急入院と育児支援入院を行っている病棟だったが、受け入れは全て中止、延期となった。個室の扉には新たに大きな窓を取り付け、監視カメラを設置、24時間観察が行えるような工事も行った。小児は状況が理解できず、目が届かないと転倒や自己抜去も考えられたためだ。

病室の扉に取り付けた窓(トリアージ病棟)

24時間観察するためカメラ設置(トリアージ病棟)
A病棟の看護職たちは、そのまま「トリアージ病棟」で対応することになり、2月中旬から、フル装備での個人防護具の着脱訓練や、技術や知識の習得が始まった。しかし、未知の感染症への不安に加え、心疾患や重い呼吸器症状のある子どもたちに関わったことがない者も多く、突然の業務内容の変更に看護職たちの戸惑いは強かった。山岸聡子副看護局長は「例えば、きちんと防護服の着脱ができていれば、感染は心配ないよということを安心のつもりで感染管理認定看護師が説明したが、当事者たちにしてみれば、じゃあ自分たちができなかったら感染するということなんだ、と逆に責任を感じて、不安を助長させてしまう場面もあった。感染症科の医師と感染管理認定看護師が何度も病棟に出向いて着脱訓練をし、話し合いも重ねた。最後は医師が“我々はスタッフも守ります”と伝えてくれたことでようやく安心してくれた」と振り返る。
ようやく軌道に乗り始めていた「育児支援入院」を断らなければならないことも、看護職たちにとっては辛かった。A病棟には助産師も多く、育児不安を抱えて孤立する母親たちのケアができないジレンマに苦しむスタッフも少なくなかった。
それでも1カ月後には、重症肺炎や人工呼吸器の子どもたちを看られるようになり、自信が付いたという声が聞かれるようになった。病棟師長も「スタッフの学びにつながった」と話しているという。
試行錯誤だったICUの再編成
ICUの再編は、千葉県内でも新型コロナウイルス感染症の患者が増加した4月に実施した。かかりつけの患児が感染し、重症化することが考えられたためだ。もともと9床あったICUのスペースを2つに分け、通常のICU(6床)と感染者用のICU(5床)に再編成した。32人のスタッフを16人ずつに分けて配置し、さらに看護職を確保するため、B病棟(神経科、形成外科、耳鼻咽喉科32床)を閉鎖。B病棟の看護職16人を2つのグループに分けて、それぞれのICUに入れることになった。NICUからも7人配置し、総勢55人で、6床と5床の2種類のICUに対応した。

個人防護服をつけ、患者さんのケアのため
入室準備(トリアージ病棟)
大変だったのは「通常ICU」に応援に入ったB病棟とICUの看護職たちだった。B病棟の看護師はこれまでに経験がない、循環動態やドレーンの管理、ICU専用の電子カルテなどに対応しなければならなかった。合間を縫ってICUの医師から、急変時の対応や肺炎の病態生理、何を看なければならないかなどレクチャーはあったが、スタッフの表情は硬かった。「やはりICUということで、緊張が強くて、通常なら十分気を付けられるのに、過緊張になってインシデント起こしてしまったこともあった。自分が動けなくなっているということに歯がゆさを感じて涙するスタッフもいた」(山岸副看護局長)。医師たちからも「このままではスタッフが潰れてしまう」と心配の声が上がった。
元からいたICUのスタッフが、パートナー制度で、マンツーマンでサポートしたり、B病棟の師長が1日1回は必ずICUを回って声を掛け、朝夕に休憩室で話を聞いたりするなどなど心理的な支援を行った。院長も「病院として頑張りましょう」と声を掛け、医師たちも時間をみてさまざまな講義や研修を行って協力してくれた。最後は「とても勉強になった」と前向きにとらえるスタッフが増えたという。
混乱を乗り越え、より強いチームを
試行錯誤の中で、環境面の課題も見えてきた。例えば「通常ICU」のスペースは、以前より狭くなったが、看護職の人数は倍となり、空間的な密集が避けられなかった。また、「感染者用ICU」の空間を確保するためGCUやNICUのベッドを別の部屋に移動したが、部屋が変わると電圧や室温が変わってしまい運用に時間を要した。応援スタッフのシフトと勤務システムを対応させるなど、事務的にもさまざまな調整が発生した。
7月現在は通常の運用に戻しているが、感染が拡大すれば、再びいずれかの病棟を閉鎖してICU人員を確保する必要がある。「とにかく1人で考えても知恵が出ない。院長以下、各病棟の師長、診療部、事務局、皆同じ方向を向いていないと意思決定で合意につながらない。意見を聞きながら、安全に。それがいちばん」と浮ケ谷芳子看護局長は言う。
7〜8月は夏休みで手術を受ける子が増え、同院が一番忙しい時期。新型コロナウイルス感染症の拡大が予断を許さない中、どう乗り切るか。「できるだけ患者さんを断らないように。混乱はあるが、これらを乗り切った後には支援しあえる仲間づくりができ、一層チーム力を高められるはず」と浮ケ谷看護局長、山岸副看護局長は決意を新たにしている。
(2020年7月7日取材)
行き場を失っている患者を断らない 〜テント診察とフロントライン〜
医療法人直心会 帯津三敬病院 看護部長 出井小幸さん
医療法人直心会帯津三敬病院(99床)は、開院以来、多様なアプローチを取り入れたがんの治療を行っている。近年では地域住民の診療も広く受け入れてきた。
「発熱したので診てほしい」という声が増え始めたのは3月末。当時は保健所のPCR検査数が限られ、発熱患者の診察を制限する病院も多かった。「行き場を失っている地域の人を断るわけにはいかない。なんとかうちで診ていこうということになった」と看護部長の出井小幸さんは振り返る。
院内感染を防ぐ4つの「関所」

①病院玄関のインターフォン
③駐車場のリモート診察用テント
院内感染を防ぎつつ、新型コロナウイルス感染症の判別がつかない発熱患者にどう対応するか。帯津三敬病院では4つの「関所」を設けた。
- ①病院玄関のインターフォン
- ②正面入り口のフロントライン
- ③無人テントでのリモート診察
- ④院内の発熱外来
−である。
発熱を訴える患者に対しては、まず①のインターフォン越しに看護職が問診する。新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は③のテントに誘導。テントの中で、患者は自ら検温、経皮的動脈血酸素飽和度※1を測定し、モニター越しに院内の看護職に見せ、医師が問診を行う。ここまではすべてリモートだ。
問診の結果、必要性があると判断されて初めて、医師、看護師、検査技師らが個人防護具をフル装備し、患者と接触。院内の検査室での肺の画像撮影や、テントでのPCR検体採取や採血を行う。個人防護具が不足する中、最小限の資源と人員で対応するために捻り出された体制だ。
それでも防護服の在庫は厳しかった。1回の「感染疑い」が出ると防護服5〜6着が必要になる。在庫がなくなれば患者を受け入れることができなくなってしまう。出井さんは毎週のように、行政に物品の在庫状況を報告していたが、支給はなく、最も不足した時は、各サイズが1セットずつしか残っていなかったという。

③患者はモニターで受診

④院内で医師・看護師が診察
皆が不安がったフロントライン
個人防護具の不足と合わせて大きな問題だったのは、無症状で感染の自覚がない患者をどう選別し院内に入れないようにするかだった。要となったのが②「フロントライン(=最前線)」だ。看護職が中心となり、各部署の職員2人で、正面玄関の風除室に立ち、全ての患者に来院目的と体調を聞く。場合によっては簡単な問診も行って感染の有無を判断し、通常診療、発熱外来、テント診察に振り分けた。院内感染予防のための、いわば「門番」だが、防護服は在庫がなく、装備はマスクと手作りのフェイスシールドのみ。1人30分と時間を区切って、病院全体でローテーションを組んだ。「当初は怖がって固辞する職員もいたが、意欲のある看護職が率先してやってくれ、こうすれば大丈夫、という感染対策の自信、蓄積ができた」と出井さん。

②フロントラインに立つ出井さん(左)
7月1日現在、テント診察で診た患者は53人。感染者は1人。今もフロントラインとテント診察は続けられており、出井さんも“最前線”に立っている。「患者さんの中には、ご苦労さまと労ってくれる人もいるが、テントが駐車場に出来ただけで“感染者がいる”と誤解され、患者さんがタクシーの送迎を断られそうになったこともある。それでも第2波、第3波が来た時、私たちは住民を守る、頑張るという意志で続けていく」。
(2020年6月24日取材)
- 1. 経皮的動脈血酸素飽和度:皮膚を通して動脈血中のヘモグロビンがどのくらい酸素と結びついているか(酸素飽和度)を表す数値。パルスオキシメーターという装置で測定する。
“コロナ渦中”の着任 専門知識が病院を変えた
救世軍ブース記念病院
副看護部長/感染管理認定看護師・特定行為研修修了者
小西直子さん
手探りで行われていた感染対策

院内研修で講師を務める小西副看護部長
東京都杉並区にある救世軍ブース記念病院(199床)は、療養病床や緩和ケア病棟を持つ地域の慢性期医療を支える病院だ。東京都で新型コロナウイルス感染症が急増し始めた4月1日、副看護部長として入職した感染管理認定看護師の小西さんは、着任早々、感染症対策の要として走り回ることになった。
同院ではそれまでICC※1やICT※2はあったものの、感染症専門の医師や看護師はいなかった。各部署での感染対策は行われていたが、個人防護具が不足する中、ガウンの使い回しや、防護服の着脱が同じ場所で行われるなど、小西さんから見ると問題もあった。
病院全体の感染対策を行うには、職員全員が感染対策の正しい知識を持ち、技術を習得しなければならない。しかし、職員は看護職だけでも159人。着任間もない小西さんは、職員はおろか、看護職の顔すら分からない状態だった。
「エビデンス」も書き込んだマニュアル

改訂した感染対策マニュアル
どうすれば1人1人に正しい知識と技術を届けることができるか。小西さんが、まずとりかかったのが、院内の感染対策マニュアルの改訂だった。
「医師が執筆したマニュアルはあったが、ウイルスとは何かという記述が中心で、具体策がなかった。病棟で発生したらどうするか、外来に来た時はどうするか、どこで防護服を着脱するかなど、エビデンスに基づき実際に“動ける”マニュアルにする必要があった」と小西さん。
マニュアルは基本知識、外来・病棟での対応、職員の健康管理を柱に2度にわたって改訂。小西さんはこのマニュアルを片手に病棟を走り回る。実際に、新型コロナウイルス感染症疑いが出て現場がパニックになった際には、マニュアルを携帯して現場に駆け付け、参照しながら、やるべきことを具体的に指示していった。「実践でやることと、マニュアルの内容が結び付いて、皆の知識の定着にもつながった」と小西さんは振り返る。また、全職員を対象とした研修会も、3密を避けつつ、1カ月余りで14回行い、対策を伝え続けた。
不安を増幅させない情報発信
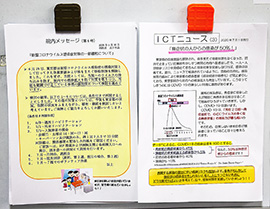
院内ニュースとICTニュース
最新の情報や院内の情報を、正確に発信することにも心を砕いた。同院にはイントラネットがないため口頭での情報伝達になり、どうしても「時間差」が生まれる。例えば「感染疑い患者」が出た場合、感染症への恐怖から、誤って情報が伝わる恐れがある。そこで毎日誰もが1度は目にする出退勤を記録するタイムレコーダー勤怠管理システムの上に、最低限の情報を貼り出し、職員の不安が増幅しないよう心掛けた。最新情報などはICTニュース、当院での対策や方針は院内メッセージとして各部署に配布し、知識のアップデートと対策の確認を促した。
変わり始めた職員たちの行動
職員たちの変化は早かった。同院が6月末に行った看護職へのアンケートでは「漠然としていたことが根拠を持って整理できた」「情報過多な時期に必要な情報を知ることができた」「必要以上に恐れず業務ができるようになった」などの声が挙がった。マニュアルや研修で具体的な方法が分かったことに加え、小西さんという専門知識を持つ存在ができたことで、これまであいまいで不安だったことを何でも聞けるようになったことが大きかったという。防護服の代わりに使えるガウンを探してくるなど、看護師たちから感染対策の積極的な提案もされるようになった。
「皆自分のことだから、真剣。特に看護職は、直接関わるので、きちんとやりたいという思いが強かった。今まではやり方が分からなかっただけ」(小西さん)。
同院では、現在までのところ感染者は出ておらず、疑いとなった患者は3人。時間がたつにつれ、職員たちも冷静な対応が可能になっているという。
小西さんは今、マニュアルを手に、救世軍法人本部や関連する介護・養護施設等の指導にも出掛けている。
(2020年6月26日取材)
- 1. ICC(Infection Control Committee、感染防止対策委員会):病院内の感染対策に関する院内全体の問題点を把握し改善点を講じるなど院内感染対策に関する審議および決定を行う。
- 2. ICT(Infection Control Team、感染制御チーム):ICCの下、実働部隊として感染対策を行うために設置される組織横断的なチーム。一般には専門知識を持った医師、看護師、検査技師、薬剤師からなることが望ましいとされている。
よりよいウェブサイトにするために
みなさまのご意見をお聞かせください